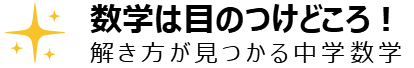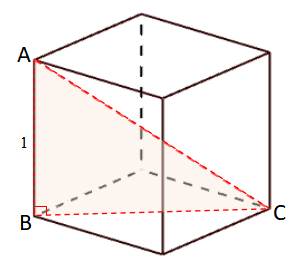確率が苦手な人ほど、つまずきやすいポイント
「場合の数・確率が苦手」という声は、とても多く聞きます。
でもその原因は、計算が難しいからではありません。
多くの場合つまずくのは、
- 何を数えればいいのか分からない
- 全体の見通しが立たない
- 条件が変わると、考え方が崩れてしまう
といった “考え方の整理” の部分です。
入試問題の確率では、
公式を知っているだけでは太刀打ちできません。
場合の数・確率は「整理の仕方」で決まる
確率の問題で大切なのは、
「全部で何通りあるのか」
その中で「条件を満たすのはどれか」
を、もれなく・重複なく整理することです。
そのために役立つのが、
- 表にして並べる
- 樹形図で分けて考える
- 同じ結果になるパターンをまとめる
といった考え方です。
計算に入る前に
「どう整理するか」を考えられるかどうかで、
解けるかどうかがほぼ決まります。
まずはチャレンジ問題に挑戦してみよう
下の問題では、
場合の数・確率を考えるときに大切な
「考え方の順番」と「整理の仕方」を意識してみてください。
最初から全部数えようとせず、
「どう分類すればもれなく・重複なく数えられるか」を考えることがポイントです。
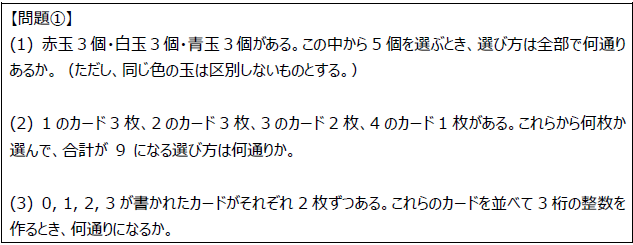
詳しい解説と解答は、こちらからダウンロードしてください。
解説では、単なる答えだけでなく、
- なぜその整理でよいのか
- 他に間違えやすい考え方は何か
といった点も解説しています。
「なんとなく合っていた」ではなく、
自分の考え方を言葉で説明できるか
を意識して確認してみてください。
次のステップへ|発想力を鍛えるドリル
さらに“場合の数・確率”を得点源に変えたい人のために、
noteでは場合の数・確率編のドリル(有料)を用意しています。
ハイレベルな応用問題を厳選し、
「どんな視点で整理すればよいか」「どんな場合分けをすればスッキリ解けるか」を丁寧に解説。
読むだけでも発想力・着想力が鍛えられます!
また、noteでは「数式」「関数」「平面図形」「空間図形」「場合の数・確率」の
各分野のドリルも公開中です。
苦手分野を集中的に鍛えたい人も、体系的に学び直したい人も――
解き方が見つかる!中学数学「目のつけどころ」ドリル集をぜひチェックしてみてください。